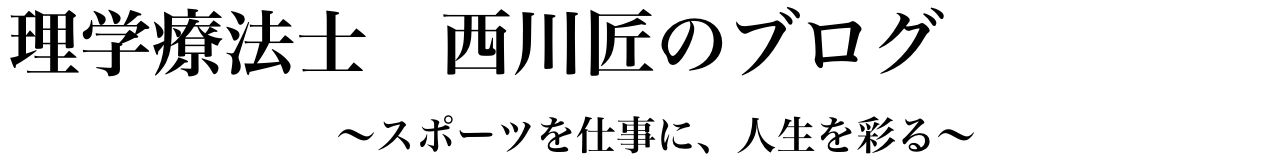こんにちは、@physio_tennisです。
もうすでにトレーナー活動している人も、これから始める人も、「自分の活動を広げたり、仕事につなげたい」という人は多いかと思います。
いろんなフェーズがあると思いますが、大体共通している主な悩みは、
・コネクションがなく、どうやって現場やスポーツ関係の人たちとつながれば良いかわからない
・多少の繋がりはできたが、どのように関係を深めていき仕事にすればいいのかわからない
といったところでしょうか。
僕が実践している、「トレーナー活動を広める、超現代的考え方」をお伝えします!
それでは始めます。
■4つの動線を組み合わせて、関係を深める
結論から。
オンライン(SNSやブログなど)とオフライン(現実世界)という、二つの軸を組み合わせて4つの動線を作り、それぞれの動線を使いこなしながらクライアントと関係を築いていくということです。
4つの動線は、こんな感じ。
①オフライン→オフライン
②オフライン→オンライン
③オンライン→オフライン
④オンライン→オンライン
…見にくいっすねw
要は、ネットと現実世界を往復しつつ、仕事していきましょうということです。
多くの人は、①のオフライン→オフラインという動線を主にイメージしているものと思います。
・スポーツ現場に直接アポを取り、現場に顔を出す
・知り合いや先輩などから紹介してもらう
・スポーツ現場が公募している案件に募集する
これらの行動は、オフライン(現実世界)が入り口であり、多くの人はここからつながった人たちと「直接会う/現場に顔を出す」ことで関係を深めていこうと考えます。
これ自体は間違いではないのですが、他の3パターンも意識できるようになれば、より効果的に関係を作って行くことが可能です。
ということで、4つの軸の詳細を一つづつ解説しますね。
①オフライン→オフライン
冒頭に書いた、最もみなさんがイメージしやすいポピュラーな方法ですね。
自分の足で現場を探し、アポをとって見学にいく。そしてボランティアとして入らせてもらい、徐々に信頼関係を作っていく。。。という手法です。
スポーツ現場は、いまだこの手法がメインであり、これからもメインであり続けるでしょう。
良し悪しなのですが、飛び込み営業に似た感覚でもあるため、勇気がないと難しいのもまた事実です。そして、飛び込んだ先の現場が自分に合わなかったりすると、それは大変です笑
このオフライン→オフラインの手法で特にハードルが高いのが、最初の「現場に入るまで」だと思います。
個人的に思うのは、多くの人はこの現場にアポをとるという行為を軽く見がちなんですよね。なんとなく良いなと思った現場に、飛び込み営業的に電話をかける、みたいな。
正直、それではうまく行かないことがほとんどなのですが。。
ちなみに、僕の周りでこの手法でうまくいった例を振り返ると、ほとんどは「リサーチ」を入念にしています。
自分が関わりたいチームや現場は、どんな監督・指導者が教えているのか。
その指導者はどんな背景で在籍されていて、どんな人物像で、チームの人数はどのくらいで、普段どんな時間帯で活動しているか。。。など。
この辺のリサーチをたくさんすることで、アポととる前に「その現場で指導者や選手が悩んでいるであろうこと」を予測することができるんですよね。
そうしたリサーチをへて、さらに時間があればそのチームの試合などをイチファンとして見に行ったり。
そこで、ファンとして挨拶をしたり、繋がりを持てるようになれば、チーム側としても気持ちよく自分のことを知ってくれるはずですし、そういったスタートする前段階から関係性がある程度できていれば、いざアポをとったりしても、現場に入らせてくれる確率は格段に高まります。
現場に入ってから全てをスタートしようという考えは、無計画であると言わざるをえません。
オフライン→オフラインは、人との繋がりが全てですから、しっかりリサーチをして、事前に少しでも関係が作れるように行動をして、そこからスタートさせていきましょう。
②オフライン→オンライン
さて、ここからオンライン、つまりSNSやブログなどのネットを絡めての関係性作りを解説していきます。
入り口は①と同じ。
自分でアポを取って現場に出て行ったり、公募にレスポンスしたりしてキッカケを作っていきます。
しかし、こうしたやり方で繋がりを持った場合、
・自分の本業が忙しくて、なかなか顔を出せない
・監督や選手たちも日々業務や勉強などで忙しく、コミュニケーションが十分に取れない
・クラブや部活に予算がなく、トレーナーに出すお金がない
といった悩みがあるあるだったりします。
そこで、こうした現場の悩みを解決するために、オンラインというテクニックを使います。
具体的には、ブログや動画などで、
・現場で指導した内容を、選手への復習の意味合いでまとめる
・その日にやったことや起きた出来事、取り組んだトレーニングなどを、保護者にシェアする意味合いでまとめる
・取り組んでいるトレーニングの目的などを、コーチとの共有を目的としてまとめる
といった感じです。
これらは、オンラインではあるものの、現実世界(オフライン)で関わっている人に向けて伝えるのが目的ですから、限定公開でグループラインなどに投稿する、といった形にするのが良いかもしれません。
僕自身は、個人的にコーチや保護者の連絡先あてにシェア用の動画やブログ記事のリンクを送ったりしていますが、これをするとお互いのスキマ時間を使って意思共有ができるため、とても喜ばれます。
現代人、とりわけスポーツ現場に関わる人たちの大きな悩みの一つは「時間」です。
みんなとコミュニケーションが取りたい、より効率的な練習やトレーニングを勉強したい、しかし時間がない。。
そんな現場に声に対して、オンラインという手段を使ってスキマ時間にシェアしてあげることで、関係性がグッと深まります。
実際、僕の周りのトレーナー仲間や、僕自身も現場と契約している間は、基本的に補足的にオンラインを活用していますが、これをボランティアの頃から徹底しておくことで、いざ仕事(有償契約)の話になったとき、すんなり提案を飲んでくれることが多いです。
信頼関係を飛躍的に高めてくれる良い方法であるので、オフライン→オンラインの動線はうまく活用しましょう。
③オンライン→オフライン
さて。
ここからは、上の二つとは動き方が一線を画したものになります。
自分の仕事を「オンライン」から広げていくという手法です。
つまり、SNSやブログで日々発信をしていき、そこからつながった個人やチームと、実際の現場でサポートしていくという流れです。
これは、時代に則したやり方でもあるのですが、スポーツ現場は時代のトレンドに乗るのが遅い傾向にあるため、まだ取り入れてない人がほとんどです。
例えばベタなやり方ですが、トレーニングや体つくりに関する自身の知見を、ツイッターやインスタ、youtubeなどで情報発信していく。そして、興味を持ってくれたフォロワーさんとコメントなどを通してつながっていき、自分がサポートできるエリアにいる場合は、実際の現場などに訪問し、サポートしていくというやり方がイメージしやすいでしょう。
ここでのポイントは二つあり、一つはSNSの発信についてしっかりと理解すること。
↑こちらの記事にも書いていますが、SNSの発信やそれに伴うブランディングは、れっきとした戦略ゲームであり、ひとまず何か発信してれば良いだろうという根性ゲームではありません。
各SNSの構造を知り、日々試行錯誤を重ねていく必要があります。
現場の仕事と同じでラクではありませんが、既出の通りスポーツの業界は多くの人がこうした発信が苦手(もしくはロジックなしの根性論だけで発信している)なため、しっかりと戦略を持って発信できれば、十分に勝機はあるでしょう。
二つ目のポイントは、つながったファンとしっかりコミュニケーションをとっていく、ということです。
僕の友人で、youutbe発信のチャンネル登録数を短期間で伸ばした人がいるのですが、彼に秘訣を聞くと、「できるだけコミュニケーションを長く続けること」と言っていました。
その彼は、youtubeについたコメント一つ一つをチェックすることはもちろん、「誰が、いつ、どんなコメントをしたのか」を一つ一つメモしており、新しくアップした動画でコメントがついたら、そのメモを振り返ることを習慣化しています。
そして、「この前もコメントしてくれましたよね!」とか、「この前コメントで言われていた〇〇の件、次の動画で解説しますね!」みたいに、1人のストーリーある人間同士の繋がりとしてコミュニケーションをとっています。
僕らは、SNSについたコメントなどを軽視しがちですが、コメントをしてくれるというのは、画面越しにストーリーある1人の人間が何かしらの感情を持って書き込んでくれているということを忘れてはいけません。
実際に、こうした一人ひとりの繋がりを意識すると、あなたの発信にファンはしっかりついていきますし、現実世界の仕事にも広がっていきやすくなるでしょう。
④オンライン→オンライン
最後は、上記のようにオンラインを通してつながった人たちと、そのままオンラインを通してサービスを提供する、という手法です。
③のオンライン→オフラインの動線は、非常に効果的な反面、現実世界で自分がサポートできる範囲(時間的、距離的)には限りがあります。
あなたが東京に住んでいて、オンラインでファンになってくれたスポーツチームが九州のチームだったり、はたまた個人が海外在住だったりすると、日常的に現実世界でサポートすることは難しいですよね。
この場合、オンラインの画面越しにトレーニングを提供したり、セルフケアやリハビリのアドバイスを提供する、などの手法が活用できます。
↑こちらのマガジン記事にも書いていますが、今後5Gが広がっていくにつれ、オンラインでのパーソナルトレーニングなどの需要はますます広がっていくでしょう。
実際にトレーナー活動をしていて僕も実感するのですが、実際に体にタッチする必要がないことって結構多くて、治療ならともかくトレーニングの場合は画面越しにオンラインで提供するのは難しくないんですよね。
SNSなど、オンラインを通してつながった人たちと、そのままオンラインで何かしらのセッションをする、というのは、とても現実的な手段で、実際僕の周りのトレーナーでも実践している人は多くいます(僕もやっています)。
そして、オンラインを通してトレーニング提供をする最大のメリットは、安価でセッションを提供できるという面です。
自前のジムでトレーニングを提供する場合、ハコモノの家賃など固定費を加味した上で利益を出さないといけないため、どうしてもセッションの値段は高く設定しなければいけません。
一方でオンラインの場合、経費はほとんどかからないので、固定費をごっそり取り除いた価格でセッションを提供することが可能なため、クライアント側としても嬉しいんですよね。
デメリットとしては、この手法はオンラインで全て完結させるため、現場特有の空気や人間関係などを把握しにくかったりします。
ここ数日間は新しい試みを色々とトライしていたのですが、やはりいくらSNSが発達していても「現場に落ちてる情報と現地との繋がり」に勝るものはないですね。僕はトレーナー活動し始めた時から『現場を拠点にする』がコンセプトなのですが、最近改めて大事だなと実感します。みんな、現場に行こう。
— 西川 匠 Takumi Nishikawa (@physio_tennis) November 9, 2019
僕は常々、スポーツは現場が拠点であるというコンセプトを持ちながら活動しているので、基本的にオンラインのみで完結するという手法はあまり好きではありません。
やっぱり、スポーツは現実世界で行われますし、1人ではできないのがスポーツで、そこに生まれる人間関係やドラマが醍醐味だったりするので、現場に行かないと何もわからないんですよね。
だから、物理的に離れていたり、オンラインで繋がるしか方法がないのであれば仕方ないですが、スポーツチームなどと関わりたいのであれば、遠くてもたまに現場に顔を出すようにしながら、オンラインのサービスも活用するのが良いと思います。
まとめると…
今回はあえて4つの手法を別々に紹介しましたが。
実際には、「オンラインとオフラインを行き来しながら、フレキシブルに活動を広げていく」というのが本質かなと思っています。
時代は明らかにアナログでは通用しなくなっていますし、かといってスポーツは現実世界で行われていることなので、デジタルが全ての世界にもなり得ません。
次世代のスポーツ産業を生きる1人の人間として、オンラインもオフラインも熟知して仕事していきたいですね!
そんじゃーね!!